
卒論の考察って何を書いたらいいんだろう。

そもそも考察って何?
このように思っている大学生も多いのではないでしょうか。
ここでは、そのような大学生の疑問に答えるために考察の書き方を実例をあげながら説明していきます。
特に、論文の各パートがどのように考察に結びついているかを実例をあげながら解説していきます。
ポイントを簡単にまとめると
考察は
- 本研究の目的で述べた課題に答えていく。
- 考察は結果の部分との違いを明確にする。
- 考察で感想を書かない。
- 考察を書く際はいいたいことを大きくいくつかに分けていく。
- 最初に結論・主張を書いて、その後に具体例を書く。
- 本研究の限界点を書く。
こちらの動画でより詳しく解説しています。
動画を見ながら、ここを読むとより理解が深まります。
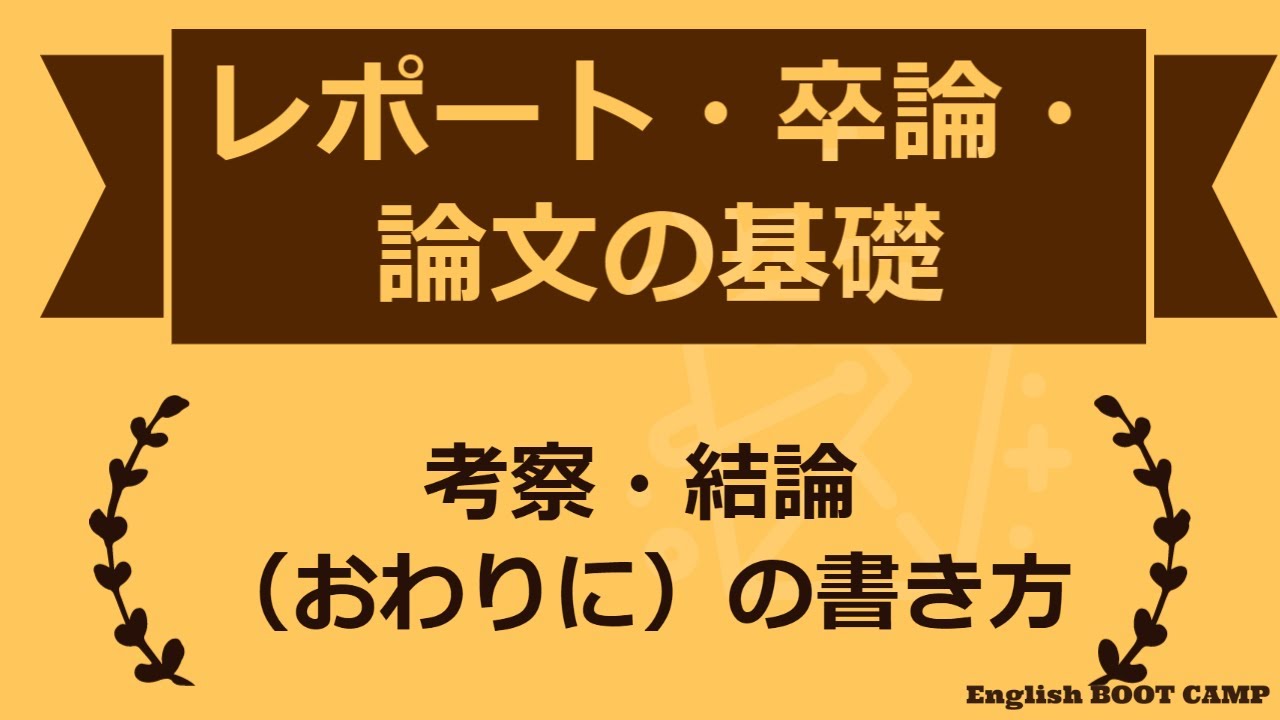
▶ 考察・結論の書き方の動画 (新しいタブで開きます)
この記事の執筆者:
大学教員/教育学博士。英語教育・論文指導を専門とし、卒論・修論・学会発表の指導歴20年以上。 『Language Learning』『The Modern Language Journal』『System』など国際学術誌の査読者を務め、学術論文の執筆数は100本以上。
レポート・卒論・論文の考察の書き方
ここではレポート・卒論・論文の考察の書き方の4つのポイントについて解説します。
ポイント1 本研究の目的で述べた課題に答えていくのが考察
考察は一言でいうと、序論の最後の問いや本研究の目的で上げた課題に答えていくところです。
つまり
序論の最後の問いを、先行研究をもとにより詳しく具体的なものにしたのが本研究の目的で、その本研究の目的の課題に具体的に答えていくのが考察です。
序論の最後の問い(漠然)
先行研究をもとに
本研究の目的(より具体的に)
本研究の目的に具体的に答えていくのが、考察
結論では序論の問いに答えていく
黄色同士・青同士がセットになります。
具体例をあげながら説明します。
これが序論の最後の問い
ゆえに,本研究では今後日本がどのような英語のデジタル教科書を小学校の英語の授業に導入していくべきかなど日本の小学校の英語教育に示唆・指針を与えていくために,韓国の小学 3 年生対象の 3 冊の英語の検定教科書のデジタル教材(e 教科書)の内容分析を行っていく。
この間にこのことに関する先行研究が入って本研究の目的ではより詳しく、具体的になっています。
本研究では,分析対象の教科書を 1 冊から 3 冊に増やし,さらに開発が進んでいる韓国
の英語の e 教科書のコンテクスト(対話者の国籍・対話場所)と談話構造(場面数,対話数,ターン数)を分析し,日本の小学校で現在使用されている『Hi, friends!』のデジタル教材の分析を行った執行・カレイラ(2016)およびカレイラ他(2016)と比較しながら,韓国の e 教科書から日本はどのようなことを学べるかを検討していく。
「考察」でははその「目的」で掲げた課題への答えを示す場ですので、「目的」にあっていなければなりません。
目的の黄色の部分が考察の黄色の部分で答えを示しています。
目的の青の部分が考察の青の部分で答えを示しています。
1つ目のかたまり
最初に対話者の国籍について考察していく。すべての e 教科書において,対話者の国籍に
関して不明なものがほとんどなく,文脈の特定化がなされているが,詳細に見てみると,そ
れぞれの e 教科書によって対話者設定において偏りがあることがわかる。
つぎに,対話場所に関して考察していく。すべての e 教科書において,対話場所に関して
も不明なものがほとんどなく,文脈の特定化がなされていた。
執行・カレイラ(2016)は現在日本の多くの小学校で使用されている『Hi, friends! 1, 2』
は,対話者の国籍に関して半数以上が,対話場所に関しては 8 割近くが不明であり,さらに,
同じような設定が多いと報告しているが,
2つ目のかたまり
場面数,対話数,ターン数では,ハン他は場面数とターン数が一番多く,対話数において
はユン他が一番多い。これらのことから,ハン他が他の二つの e 教科書よりも,多くの聞く
活動およびそれに準ずる活動部分,
これらの結果をカレイラ他(2016)の『Hi, friends! 1』と比較してみると『Hi, friends! 1』
は「各項目に収録されている対話数や,対話をなすターン数も一定ではない」(カレイラ他,
2016,p. 79)ため,対話のやり取りが定型であり
こちらの論文>>>韓国の小学3年生対象の英語のe教科書の内容分析
ポイント2 考察は結果の部分との違いを明確にする
結果は分析結果を無味乾燥(自分の感情を入れずに)に書いていきます。
一方で考察は結果をもとに、それらをまとめたり、組み合わせたり、分解したりしながら自分の意見を書いていく部分です。
つまり、結果をまとめたり、組み合わせたり、分解したりしながら序論で立てた問いに答えていくのです。
ここが著者の腕の見せ所です。
ポイント3 考察で感想を書かない
時々、卒論で結果に対する感想を書いてくる学生がいます。
「いい結果が出てよかった。」などという感想を考察に絶対に書かないようにしましょう。
考察は感想を述べる部分ではなく、結果から客観的に判断できる自分の意見を書く部分です。
ポイント4 考察を書く際はいいたいことを大きくいくつかに分けていく
考察では、結果や自分がいいたいことなどを大きくいくつかのかたまりにまとめてください。
具体的には、「ここではフィンランドの教育が成功した要因を5つに分けて解説する」と書いて、その後に、序論で提示した問いの答えを以下のように、3~5つぐらいに分けて解説していきます。
第一に、(「第一に、」と句読点を入れることが多いです)
第二に、(「第二に、」と句読点を入れることが多いです)
次に、(「次に、」と句読点を入れることが多いです)
最後に、(「最後に、」と句読点を入れることが多いです)
というように、その大きなかたまりを順番に、結果と先行研究を示しながら書いていきます。
具体的には、「ここではフィンランドの教育が成功した要因を5つに分けて解説する」と書いて、その後に、序論で提示した問いの答えを以下のように、3~5つぐらいに分けて解説していきます。
最初に対話者の国籍について考察していく。すべての e 教科書において,対話者の国籍に
関して不明なものがほとんどなく,文脈の特定化がなされているが,詳細に見てみると,そ
れぞれの e 教科書によって対話者設定において偏りがあることがわかる。
ハン他では
イ他では,
ユン他では,
つぎに,対話場所に関して考察していく。すべての e 教科書において,対話場所に関して
も不明なものがほとんどなく,文脈の特定化がなされていた。詳細に見ると,おおむねどの
e 教科書も animation 以外は,家,戸外,学校に分類されるが,イ他やユン他では,そのい
ずれもがおおよそ等比率で登場している。これは子どもの身近な場所のどこにおいても学習
場面数,対話数,ターン数では,ハン他は場面数とターン数が一番多く,対話数において
はユン他が一番多い。これらのことから,ハン他が他の二つの e 教科書よりも,多くの聞く
活動およびそれに準ずる活動部分,
ポイント5 最初に結論・主張を書いて、その後に具体例を書く
言いたいことをわけたら、段落にわけますよね。
その場合、パラグラフ・ライティングの手法を取り入れてください。
パラグラフとは段落のことで、パラグラフ・ライティングとは一言でいうと、「各段落は、トピックセンテンスを最初に書いて、その後に、具体例を書く」ということです。
トピックセンテンスというのは、その段落で、いいたいこと、つまり、主張・結論・理由などです。
つまり、最初にその段落の主張・結論を書いて、その後に、具体例を書いてください。
もっと簡単にいえば、最初に重要なこと・結論を伝えて、詳しいことは後にということです。
そうすると各段落の最初の文章だけ読むだけで、そのレポートでいいたいことがわかるようになります。
上記の「ポイント3 考察を書く際はいいたいことを大きくいくつかに分けていく」の実例をもとに解説しますと、
つぎに,対話場所に関して考察していく。すべての e 教科書において,対話場所に関しても不明なものがほとんどなく,文脈の特定化がなされていた。
の部分がトピックセンテンスで、最初に結論を書いています。
詳細に見ると,おおむねどのe 教科書も animation 以外は,家,戸外,学校に分類されるが,
というように、その後に詳細が書かれています。
このように最初に結論、その後に詳細というように書いていきましょう。
ポイント6 文字数が少なくて困ったなら、本研究の限界点を書く
あとはよく本研究の限界点を書きます。
完璧な論文なんてありませんので、限界点は探せばいろいろできてきます。
これは異なる論文からの抜粋です。
最後に本研究の限界点について述べていく。第一に,本研究では日本人がオーナーである
と思われる日本資本の和食店と日本人以外がオーナーであると思われる海外資本の和食店の
2 つに分けて分析を行ったが,明らかに日本人がオーナーである和食店はいくつかあったが,
オーナーが外国人でも日本人シェフが取り仕切っている和食店やオーナーが日本人と他国の
ハーフであるなど判別が難しい和食店もあった。便宜上,日本資本,海外資本という言葉を
使ったが,それらが必ずしも正確に定義されているとはいえない。第二に,本研究はイギリ
スのロンドンに限って調査を行った。今後はアジア,アメリカなど他の地域での調査を行い,
それらの結果を比較することにより海外における和食点の現状をより正確に把握することが
できるであろう。
ただし、限界点は結論に書く場合もあります。
結論の書き方はこちら>>>おわりに・結論の書き方はこちら
レポート・卒論・論文の全体構成
最後に論文の全体の構成についてまとめます。
- 序論(問いをたてる・漠然)を参考に
- 先行研究(その問いに関連して今までどんな研究がなされているのかを提示)
- 本研究の目的(先行研究を踏まえて、序論の問いをより詳しく具体的に)
- 方法(その目的を達成させるための方法を示す:他の論文から型を真似る)
- 結果(無味乾燥に書く・自分の感情は入れない:他の論文から型を真似る)
- 考察(本研究の目的であげた課題に答える)
- おわりに(考察を簡単に1~2段落にまとめる・序論の問いに答えていく)
上記の各部の詳細は以下のリンクで学習してください。
序論(問いをたてる・漠然)
先行研究
先行研究の資料の探し方は以下の2つを参考に。
先行研究の引用の仕方は以下を参考に。
おわりについての詳細は以下を参考に。
全体
全体の構成を通して学習したい場合は以下を参考に。
就活と卒論
AIツールを活用して考察を深めよう
考察を書く際には、先行研究を整理しながら、自分の研究結果との違いや新しい発見を論理的に説明することが求められます。とはいえ、論文を大量に読み込んで理解し、要点をまとめるのは大変です。そこで役立つのが、研究者向けに特化したAIツールです。
皆さんがよく使うChat GPTやGEMINIは平気で架空の論文を出してきたり、かなり間違ったことをそれらしく言ってきます。私がこれらを使うときには、「これ違うんじゃない」「こうだよね」と指摘しまくっていますので、「ご指導ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします」という回答が来ることもあります。慣れてくると「こういうときにはこのAI」、「ここではこのAI」というように分けて使うととても便利なのですが、皆さんはそういうことができないと思いますので、最初から論文執筆に特化したAIを使ったほうが安全です。Chat GPTやGEMINIの「嘘」を見破り、的確な指示を与える自信がないのなら、これらを論文執筆で使うのは絶対やめましょう。大変なことになります。
とくに次の2つは、研究や論文執筆の「相棒」として高く評価されています。
- SciSpace:PDFを読み込み、要約や関連研究の抽出・質問応答まで行える研究特化AI。日本語にも対応し、文献理解に最適です。また、書いた論文も丁寧に査読してくれるため、研究者や大学院生におすすめです。
- Paperguide(PaperGuide AI):研究テーマを入力すると、論文構成や文章の流れを自動的に提案。さらに「Deep Research」機能で先行研究を検索し、引用付きレビューを生成してくれます。コスパの良さも人気の理由です。
どちらも無料プランから利用可能で、英語・日本語どちらの文献にも対応しています。AIを活用することで、論文の読み込み時間を短縮し、考察の質を高めることができます。
卒論執筆におすすめのパソコン環境
WordやPDFでの卒論作成には、快適に動作するパソコンが欠かせません。特に締切前にフリーズや不具合が起きると、大きなストレスになります。
筆者のおすすめは、法人リースで使われていた高性能な中古ビジネスノート(レッツノート・ThinkPadなど)。耐久性がありながら価格も抑えられており、学生にも人気です。
ただし、中古パソコンは「どこで買うか」が非常に重要です。保証・返品対応・初期設定の有無などを確認して、信頼できる専門ショップから購入するようにしましょう。
比較して選んだ、安心&お得な中古パソコンショップはこちら:
より詳しいレビュー・注意点は以下の記事で解説しています。
まとめ
この記事では、卒論の「考察」の書き方を中心に、論文全体の構成や注意点について詳しく解説してきました。
問いの立て方から始まり、先行研究、目的、方法、結果、考察、そしておわりに――この一連の流れを意識することで、読み手に伝わりやすく、評価される卒論に仕上がります。
また、卒論を執筆する際は、作業環境=パソコンにも注意が必要です。動作が遅かったり、フリーズしたりすると、締切直前の大事な時間を無駄にしてしまいます。
筆者のおすすめは、法人リース落ちの中古ビジネスノート(レッツノートやThinkPadなど)。高性能で丈夫、価格も手ごろなので学生にも人気があります。
中古パソコンは「どこで買うか」が非常に大切。信頼できる専門ショップを選びましょう。
以下は、筆者が比較して選んだおすすめショップです:
- 👉 【PC WRAP】3年長期保証&即納対応!初心者も安心の老舗ショップ
- 👉 【パソコレ】楽天ポイント最大20倍!コスパ最強&即日発送多数
- 👉 【Qualit】新品級の美品多数!価格と品質のバランスが抜群
卒論執筆をやりきったあなたに、少しでも役立つ情報となれば幸いです。快適な作業環境を整え、AIツールや信頼できるパソコンを活用しながら、より完成度の高い論文を目指しましょう。
最後まで粘り強く考察を書き上げる経験は、きっと社会に出ても大きな財産になります。






