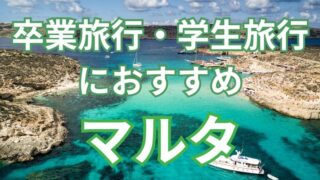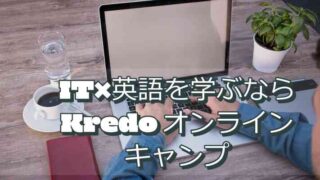MaaSという言葉を聞いたことがありますか。
ここでは、MaaSについて何も知らない方のために、MaaSとは何なのかを最初に解説し、MaaSがなぜフィンランドで始まったのか、さらに、フィンランドのMaaSの事例・背景・効果についてわかりやすく解説します。
さらに、海外のMaaSの成功事例についても解説します。
なお、MaaSについての卒論を書く学生さんのために、MaaSに関する書籍・論文・資料の一覧も掲載しました。
ご活用ください。
MaaSとは?
MaaSとは「Mobility as a Service」の略で「マース」と発音します。
MaaSについては、国土交通省(2018)が以下のように説明しています。
MaaSとは、ICT(Information and Communication Technology)を活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)を一つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念である。利用者はスマートフォンのアプリを用いて、交通手段やルートを検索、利用し、運賃等の決済を行う例が多い。2015年のITS世界会議で設立されたMaasアライアンスでは、「Maasは、いろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合することである」とされている
国土交通省(2018)より引用
つまり、MaaSはICTを活用してマイカー以外の全ての移動を一つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな移動の概念です。
「モビリティ」を直訳すると「移動」「機動性」「可動性」などで一般的には「交通手段」そのものを指すこともありますが、広義には「移動のしやすさ」ということができます。
MaaSは、特に移動に関する新しい概念なので移動のしやすさを従来の交通手段であるマイカーや電車などの「モノ」の提供ではなく「サービス」によって実現するという意味合いが込められています。
MaaSとSDGsの関係
MaaSの実現がSDGs(Sustainable Development Goals)に繋がるといわれている。
SDGsの詳細はこちら>>>海外の持続可能な観光「サスティナブルツーリズム」の成功例
MaaSは、このSDGsの目標のうちの、「11住み続けられるまちづくりを」という目標と深く関わっています。
「住み続けられるまちづくり」という目標では、脱炭素や大気汚染などを減らすことで持続可能な社会の実現を目指しています。
つまり、MaaSにより、車利用が減り、脱炭素や大気汚染などにつながるのです。
MaaSの5段階
Sochor ら(A topological approach to Mobility as a Service)はMaaS を以下の5段階に分類しています。
- レベル0(No integration: Single, separate services)
鉄道、地下鉄、バス、タクシー、レンタカーなどの事業者が、それぞれの移動手段に関するサービスを個別に展開しているだけで統合が行われていない段階です。これは MaaSとはいいません。 - レベル1(Integration of information: Multimodal travel planner, price info)
情報の統合が行われ、鉄道、地下鉄、バスなどの時刻や経路、料金やレンタカーなどの事業所や駐車場の場所など、異なる交通手段の情報を統合したサービスが提供されている状態です。いわゆる株式会社ヴァル研究所の「駅すぱあと」やジョルダン株式会社の「乗換案内」などがレベル1のサービスです。 - レベル2(Integration of booking &payment: Single trip-find, book and pay)
統合された情報のもとで、最適な移動手段を選択し、予約、発券、決済がひとつのアプリで行える状況です。「my route」などのマルチモーダルなルート検索サービスなどがレベル2に該当します。 - レベル3(Integration of the service offer (Bundling / subscription, contracts, etc.))
サービス提供の統合が行われており、事業者の垣根をなくし、それぞれの移動手段を一元的に提供している状況です。最適な移動手段の選択、予約、発券、決済に加えて月額制のサブスクリプションを導入することで、そのつどの決済の煩わしさから利用者を解放できます。フィンランドの「Whim」がレベル3に該当します。 - レベル4(Integration of societal goals (Policies, incentives, etc.))とは、都市計画などの政策やインセンティブなどが交通政策と一体化する段階です。
MaaSがフィンランドで誕生した背景

MaaSの概念を提唱したのはフィンランドのベンチャー企業MaaS Globalを創立したサンポヒエタネン氏です。
2006年に構想が生まれ 公的組織や大学などで研究が進められ、公式の場でMaaSが初めて披露されたのは2014年アルマト大学の工学部生がMaaSをテーマとした発表を行った時で、国内外のメディアで大きく取り上げられました。
そして2014年末にヴァンターのフィンランドサイエンスセンターでキックオフイベントが開催されました。
そこの基調講演でヒエタネン氏はビジネスプランを公表し、プロジェクトをすぐに始めたいと聴衆に呼びかけました。
多くの組織が賛同したことで事業化に向けた動きが始まり、2015年MaaS Finlandという組織を設立しました。
さらに、2015年10月にフランスのボルドーで開催されたITS世界会議で世界的に注目されるようになり、ヒエタネン氏は2016年初めに代表に就任すると世界展開を目指しMaaS Globalに社名を変更しまいした。
2016年6月には英語で気まぐれを意味する「Whim」と名付けたアプリのテスト運用を始め、10月に本格的なサービスを始めました。
ヒエタネン氏が目標としたことは「あらゆるモビリティサービスを組み合わせて車を所有する生活よりもより良い生活を実現するサービスを作り出すこと」です。
あらゆるモビリティサービスと、自転車シェアリングやカーシェアリングなどの「次世代モビリティサービス」と組み合わせることにより、マイカーを所有するより環境面でもより良い暮らしができることを目的としています。
ところで、都市部の車を減らし、環境にやさしい移動手段に転換しようとしており、事実、マイカーをバスや電車といった公共交通に切り替えたり、長距離トラック輸送を貨物列車や貨物船との併用にするなど、多様な輸送手段を組み合わせることで環境負荷を減らすマルチモーダルの考え方は古くからありました。
ゆえに、 MaaSは従来のマルチモーダルの考え方に次世代モビリティサービス(カーシェアリング、自転車シェア、自動運転、駐車場 予約など)を組み合わせたものともいえます。
つまり、フィンランドのMaaSは、次世代モビリティサービス を組み合わせたマルチモーダルが特徴といえます。
ところで、交通分野はバス、タクシー、鉄道、船舶などの種類ごとに事業法があります。
フィンランドにおいても、バス、タクシー、鉄道、などの交通事業者ごとに異なる規制で市場を調整していました。
しかし、交通事業の多くは赤字で、補助金の支出がかさむことが自治体や国の悩みの種となっており、さらに、MaaSを加速させるためには各交通事業者を縛る規制の撤廃が必要でした。
よって、2018年フィンランド政府は交通サービスに関する法律を施行し、自動車、鉄道、航空、船舶など事業者ごとに分化していた法律を一本化しました。
具体的には、規制を段階的に撤廃し各事業者独自に持つデータとAPIのオープン化を行いました。
データとAPIのオープン化が実現すれば、事業者の垣根を超えた、まさにMaaSらしい交通サービスの創出が可能になります。
つまり、法改正以前は事業者に分割されていた利害関係が、MaaSという思想的背景のもと、各事業者が独占していたテクノロジーやノウハウを皆で共有することになり、「利用者視点に立ったサービスの提供」に繋がっていったのです。
MaaSがなぜフィンランドで始まったのか?

MaaSは上述しましたように、フィンランドで生まれました。
ではなぜ、フィンランドでMaaSが始まったのでしょうか。
以下ではその理由を解説します。
運輸と通信の分野を一つの組織が担当
フィンランドには首相府、財務省、運輸通信省など 12の省があります。
MaaSを担当しているのが運輸通信省ですが、 注目すべき点は運輸と通信の分野を一つの組織が担当しています。
運輸は国土交通省、通信は総務省に分かれている日本よりも、運輸と通信の分野を一つの組織が担当しているのは、ICTによる交通改革を進めやすい体制であるといえるでしょう。
フィンランドには自動車メーカーがない
もう一つの理由として、フィンランドには自動車メーカーがないということがあげられます。
MaaSが多くの人に受け入れられると、必然的に自動車の販売台数は減少することが容易に予想できます。
これは自動車メーカーにとっては歓迎すべきことではありません。
しかしフィンランドには自動車メーカーがないため、そのような支障がありません。
ゆえに、MaaSがフィンランドで最初に始まった理由の一つでしょう。
なお、フィンランドのMaaS導入には「ITSフィンランド」というシステムが大きな役割を果たしました。
ITSとは、人と道路と自動車の間で情報の受発信を行い道路交通が抱える事故や渋滞環境対策などさまざまな課題を解決するための高度道路交通システムのことです。
世界初のMaaSアプリ「Whim」

世界で初めてMaaSを具現化したアプリは「Whim」です。
「Whim」はサンポヒエタネン氏が発案したもので、利用プランは4つあります。
- 「Whim Urban30」
- 「Whim Weekend」
- 「Whim Unlimited」
- 「Whim to go」
「Whim to go」以外は定額制です。
フィンランドのMaaSの効果
「Whim」の利用のトリップ回数は2018年7月に100万回を記録すると、10月には200万回、年末には250万回と加速度的に増えています。
MaaS Globalのアンケートでは、「Whim」を利用する理由で圧倒的に多いのは「オールインワン」であり、全体の半数近い46%を占め、2位の「使いやすさ」の15%を大きく引き離しています。
この「オールインワン」という言葉にはマイカー以外のあらゆる交通手段を一つのアプリで使えるだけでなく、運賃の支払いも行えることも含まれており、MaaSのシームレスな部分が評価されているといえるでしょう。
さらに同社が2018年に発表したヘルシンキのデータではそれまで48%高かった交通利用率は 74%にまで跳ね上がり、マイカーの利用率は40%から20%に減少したという数字が出ています。
Whimはヘルシンキの移動そのものを大きく変える力を持っているといえるでしょう。
フィンランドのMaaSに関する論文・資料
以下はフィンランドのMaaSに関して学べる論文や記事の一覧です。
フィンランドのMaaSに関する卒論を書かれる方は参考にしてください。
- 観光産業へ向けたMaaSの活用可能性
- ヘルシンキ周辺の交通システムとMaaS
- LIGAREビジネスセミナー MAR.2019 MaaS市場は、新規参入でブランドを高める時代へ フィンランド発Kyytiの取り組みから学ぶ
- 地方版ライドシェアサービスで移動弱者解消を目指す フィンランドの画期的なMaaS事業者Kyyti
- MaaS先進国 フィンランド MaaS実現化の鍵はゲーム産業の興隆とスタートアップ支援 フィンランド大使館商務部上席商務官
MaaSに関する資料・論文・本
以下ではMaaSに関する資料・論文・本をご紹介します。
MaaSに関する卒論を書かれる方は参考にしてください。
- 日本版MaaSの推進
- MaaS関連データ検討会
- 令和2年度日本版MaaS推進・支援事業 38事業
- スマートモビリティチャレンジ
- 北海道MaaS推進研究会
- 観光地型MaaSの現状と展望(株式会社日本政策投資銀)
- MaaS の現状と今後の展開に関する一考察
- 観光産業へ向けたMaaSの活用可能性
- シンガポールにおけるMobility-X社によるMaaSの取り組み
- MaaSの現状と動向
- 観光地型MaaSの現状と展望-新常態における”観光立国”関西の飛躍に向けて-
- 欧州の統合的公共交通システムと都市デザインー
- モビリティサービスの進化が街を変える —世界の事例から
- モビリティクラウドを活用したシームレスな移動サービスの動向・効果等に関する調査研究
- 国土交通省「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会中間とりまとめ」平成31年3月14日
MaaSに関係する海外での研究
イギリスのMaaS研究所
- MaaSLab(University College London)
MaaSの基礎的な概観を理解するには、一番のおすすめの本です。
- 【第1章】MaaSとは何か
- 【第2章】MaaSへと至るさまざまな交通改革
- 【第3章】MaaSの礎となるデジタルテクノロジー
- 【第4章】海外のMaaS実例
- 【第5章】MaaSと自動車メーカー
- 【第6章】日本版MaaSの作り方
- 【第7章】日本オリジナルの観光型MaaS
- 【第8章】日本ならではの地方型MaaS
- 【第9章】ラストマイルMaaSをどうするか
フィンランドのMaaSに関して、随所に記載されています。
2018年出版とちょっと古いですが、ベストセラーになった書籍です。
もう少しフィンランドのMaaSについて本格的に学びたい方は、こちらがおすすめです。MaaS Globalを創立したサンポヒエタネン氏のインタビューが掲載されています。
- MaaSは危機か、それとも輝ける未来か
- モビリティ革命「MaaS」の正体
- なぜMaaSのコンセプトは生まれたのか
- 【Interview】 MaaSグローバル Sampo Hietanen(サンポ・ヒータネン)氏
- 日本におけるMaaSのインパクト
- 「新モビリティ経済圏」を制すのは誰か?
- 【Interview】 東京大学 生産技術研究所 須田義大氏
- プラットフォーム戦略としてのMaaS
- 【Interview】MaaSアライアンス Piia Karjalainen(ピア・カルジャライネン)氏
- テクノロジー戦略としてのMaaS
- MaaSで実現する近未来のスマートシティ
- 産業別MaaS攻略のアクションプラン
その他MaaSについて学べる本をMaaSに関する書籍一覧にまとめました。
海外のMaaSの現状
最後にフィンランドで始まったMaaSがどのように世界に広まっているのかをご紹介します。
ポルトガルのMaaS
まずは、ポルトガルです。
ポルトガルは実はかなりMaaSに力を入れています。
カスカイスのMaaS

ポルトガルで一番進んだMaaSを行っているのはカスカイスです。
カスカイスのMaaSサービスは、Mobicascaisという名前で提供されています。このサービスは、市内のバス、トラム、および電車の路線やスケジュールを統合し、利用者にとってよりスムーズで便利な移動手段を提供しています。
Mobicascaisは、カスカイス市内の公共交通機関に加えて、タクシー、自転車シェアリング、カーシェアリング、電動スクーターシェアリング、および電動自転車シェアリングなどのモビリティサービスを統合しています。利用者は、スマートフォンアプリを介して、簡単に移動手段を検索し、予約、支払いをすることができます。
上記の写真はMobicascaisのバスです。
観光客も気軽に乗ることができ、私も乗ってみましたが、とっても中が綺麗です。
1日乗り放題で2ユーロでした。
こちらはカスカイスの電動バイクです。

Mobicascaisの利用者は、モバイルアプリを使用して、リアルタイムの交通情報や最適なルート、到着時間の予測などを入手することができます。
また、利用履歴の確認や支払い履歴の表示も可能です。
Mobicascaisは、ポルトガルの首都リスボンに提供されているMaaSサービスと同様に、持続可能で地域社会に配慮したモビリティを目指しています。
利用者は、自動車の利用を減らし、公共交通機関や持続可能なモビリティサービスの利用を増やすことで、温室効果ガスの排出削減に貢献することができます。
カスカイスはSDGsも積極的に進めています。
詳しくはポルトガルのSDGsをご覧ください。
コインブラのMaaS
コインブラは、ポルトガルの中央部に位置する都市で、約14万人の人口を抱える大学都市です。
コインブラにおいては、公共交通機関や自転車シェアリング、カーシェアリング、タクシーなどの移動手段を統合したMaaSサービスが提供されています。
コインブラのMaaSサービスは、市内の公共交通機関を運営するSMTUCが中心となって提供されており、ユーザーはSMTUCのMaaSアプリをダウンロードすることで、さまざまな移動手段を簡単に検索・予約・決済することができます。
具体的には、SMTUCのバスやトロリーバス、自転車シェアリングサービスのb-interactive、カーシェアリングサービスのDriveNow、タクシー配車アプリのmytaxiなどが統合されており、ユーザーはアプリ上で目的地や出発時間、予算などを設定することで、最適な移動手段を提案してもらうことができます。
また、アプリ上で予約や決済も簡単に行えるため、移動の手間を大幅に省くことができます。
コインブラのMaaSサービスは、市民の交通手段の多様性や、移動の利便性向上に貢献しています。
リスボンのMaaS

リスボンでは、Google mapで道を検索すると、キックボードや電動バイクなどでのルートや料金・時間も同時に表示されます。
Google map上から各会社のWEBサイトへのリンクがありますので、そこからキックボードや電動バイクを借りることができます。
上記のようなキックボードがリスボンの主要な場所にありました。
その他、リスボンではLisboa Cardという観光客向けのカードも有名です。
Lisboa Cardはリスボン市内の公共交通機関や観光地の入場券などを統合したものです。
Lisboa Cardを利用することで、地下鉄、バス、トラム、エレベーター、そしてリスボン市内の電車などの公共交通機関を利用することができます。
また、Lisboa Cardには、リスボン市内の主要な観光地や博物館などの入場券が含まれています。
Lisboa Cardは、利用期間や利用する場所によって価格が異なります。
利用者は、Lisboa Cardの公式ウェブサイトやリスボン市内の観光案内所で購入することができます。
リスボンのMaaSサービスは、利用者にとって非常に便利で、リスボン市内の移動や観光をよりスムーズに楽しむことができます。
また、Lisboa Cardの購入により、入場料などの支払いが現金での支払いよりも割安になる場合もあります。
ポルトのMaaS
ポルトにもAndanteという交通カードがあり、これがポルトのMaaSといえるでしょう。
Andanteは、ポルトガルのポルト市および周辺地域で使用される公共交通カードシステムです。Andanteカードを使用することで、地下鉄、バス、電車、フェリーなどの様々な公共交通機関を利用できます。
Andanteカードは、オンラインで購入することができますが、ポルト市内の地下鉄駅やバスターミナルでも購入できます。
カードには、チャージすることができるプリペイド式と、定期券を購入することができる定期券式の2種類があります。
Andanteカードは、ポルト市内の地下鉄、バス、電車、フェリーに加え、周辺地域の公共交通機関でも利用することができます。Andanteカードは、乗車回数に応じた料金が自動的に計算され、利用者にとって便利なシステムです。
Andanteカードは、ポルト市内および周辺地域での公共交通機関を利用する際に、非常に便利なものです。
Andanteカードを使用することで、乗り換えの手間や料金の心配がなくなり、スムーズな移動が可能となります。
台湾の高雄のMaaS
台湾の高雄もMeNGoというMaaSで有名ですね。
MeNGoは高雄MRT、高雄ライトレール、都市バス、市外バスなどを乗り放題可能なプランを提供しています。
MeNGoは日本語のサイトもあります。
公式サイト>>>MeNGo
なかなか便利なサイトで、自分の近辺でどのような交通手段があるのか以下のように示してくれます。

高雄ではライトレール(路面電車)を主に使いました。

ライトレールは観光客にとってとても使いやすい乗り物です。
綺麗で、料金も安いし、英語のアナウンスもあり、次はどこの駅かも電光掲示板しっかり示してくれます。
アメリカのシアトルのMaaS
シアトルには、MicrosoftやAmazonなどの大手企業の本社があるため多様な移動サービスがあります。
特に、シアトルのタコマ国際航空の空港出口にある案内板には日本では見られない多くの交通手段が示されており、日本でも馴染みのあるホテルへのシャトルバス、路線バス、タクシーなどのほか、乗り合いによるバンプール(シャトル・エクスプレスと呼ばれ、ドライバーに行き先を告げるとそこまで運んでくれるサービス)や、ライトレール(アメリカではLRTと呼ばれ、空港と都心や大学等を直結している鉄軌道の輸送サービス)、UberやLyftなどの配車サービス、カーシェアリング、自転車シェアリング、バンプール、配車サービス、電動キックボードなど様々な交通手段があります。
そして、都市部の公共交通は、ゾーン運賃制となっており、シアトル内のゾーン運賃制では都市圏内のゾーン内で、どの交通手段に何度乗り継ぎや、再乗車をしても2時間以内であれば運賃は一律に設定されています。
また、運賃の支払い方法も、交通系ICカードでキャッシュレスに支払いをすることができ、モバイルアプリを利用することでチケットレスとキャッシュレスを実現しています。
この結果、マイカーでの通勤は減り、マイカー以外の利用が75%を占めており、徐々にMaaSの実現を形にしてきているシアトルでは、シェアリングと自動運転が融合したSAV(Shared Autonomous Vehicles)が将来の移動サービスの形となるであろうと考えられています。
これらは以下の本を参考にしました。
もっと詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
おわりに
ここでは、MaaSの定義、MaaSの5段階、さらに、MaaSがなぜフィンランドで始まったのか、さらに、フィンランドのMaaSの事例・背景・効果についてわかりやすく解説しました。
なお、MaaSに関する卒論を書かれる方は以下も参考にしてください。
卒論テーマの選び方
卒論を書く大学4年生のための教材
レポート・卒論・論文の各パートの書き方