「レポートの資料ってどこでどのように集めたらいいのだろう」
「論文ってそもそもどこで入手できるのかな」
「Wikipedeaってレポートの引用に使っていいのかな」
などなど大学生の方は、たくさんの疑問があると思います。
そこでここでは、レポート・卒論・論文の先行研究(資料・文献)をどのように探したり、集めたりするかについて解説します。
具体的には以下の7つの方法について解説します。
- 大学の図書館のリソースを活用
- Wikipedia
- サイニィCiNii
- Google・Google Scholar
- 国立国会図書館
- 各県市町村などのホームぺージ
- アマゾン
そもそも何に書こうか、決まっていない方は、まずはテーマをある程度決めてください。
テーマがまだ決まっていない方は、まずは以下の2つを参考にしてください。
論文や卒論を進める上で、コストを抑えながらも快適にリサーチを進めたい学生にとって、楽天モバイルのプランは非常におすすめです。
大学生のための楽天モバイルガイドで、学生向けの楽天モバイルの特典やお得な契約情報を詳しく紹介しています。
自己紹介
大学の教員で卒論指導を毎年行っています。国際誌・学会誌・大学紀要などに100本以上の論文を発表してきました。Language Learning, The Modern Language Journal, Systemなどの国際誌の査読者もやっています。
先行研究(資料・文献)をなぜ集めるのか
小中高校でよく書いていた作文・小論文とは
- 作文(感想文):自分の感想を述べる文章(=感じたこと)
- 小論文:自分の意見を主張する文章(=考えたこと)
であり、自分の感想や意見を書くものです。(詳しくは作文・小論文・レポート・卒論の違いをご覧ください)
一方、大学に入ってよく聞くレポート・論文(卒論)というのは、これらとは全く異なります。
論文というのは主観を入れずに客観に徹して自分の解釈や意見は書きません。
自分が立てた問い・課題に応えるために他人の論文や資料を証拠として出していくのです。
そのため他の人が書いた論文すなわち引用が一つもないような論文というのはそれは論文とはいえないのです。
そのため、ある程度テーマが決まったら、最初に行わなければならないのが、そのテーマに関連した先行研究(文献・資料など)を探して集めることなのです。
そのため文献・資料を集めることが非常に重要な作業になってきます。
詳しくは正しいコピペ(引用)の仕方を参考にしてください。
大学の図書館のリソースを活用
まずは、自分の大学の図書館の図書や大学が契約している新聞や雑誌のデーターベースなどを利用しましょう。
データーベースの存在も知らない方も多いようなので、まずは、自分が所属する大学がどのようなデーターベースを持っているのかを調べてみましょう。
所蔵している本・使い方は大学により異なりますので、各大学の図書館のホームページで確認してください。
Wikipediaの使い方
Wikipediaは誰でも編集できる,フリーなオンライン多言語百科事典です。
Wikipedia自体が「引用の塊」で、オリジナル(もとの)情報源があります。
そもそもWikipediaに書かれていることを卒論・論文に使えるのか?といういいますと、答えはイエスであり、ノーです。
最初に自分の調べるテーマの資料を集めるために、WikipediaをみてもOKです。
ただし、そこに書かれてあるもとの出典、つまり、下のほうに、関連項目、外部リンク、脚注などたくさんのリンクがあると思いますので、そこをクリックしてそちらを見るようにしてください。
つまり、資料集めにWikipedia使ってもOKですが、論文の引用文献には書かないでください。必ずもとの出典を見る必要があります。
もっと詳しい解説はこちらをご覧ください。
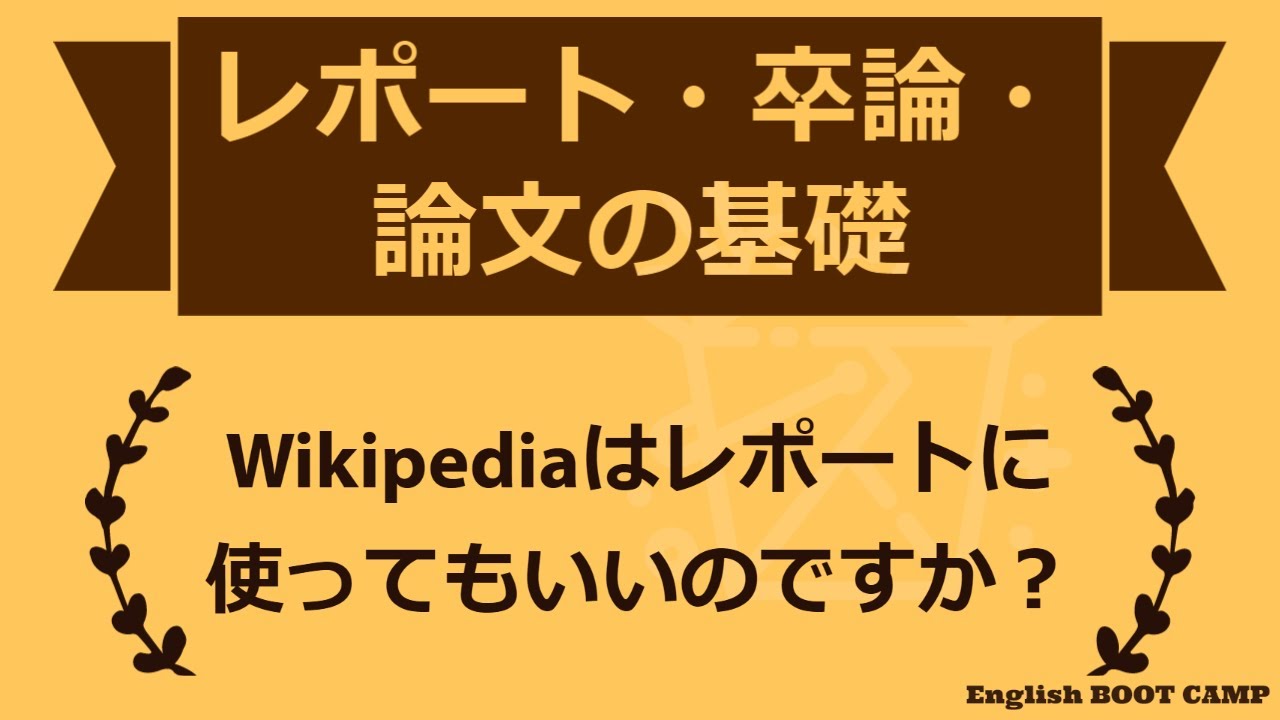
▶ Wikipediaの使い方の動画 (新しいタブで開きます)
サイニィCiNiiの使い方
レポート・卒論・論文の執筆に必須である日本国内の学術論文を検索できるデータベースCiNii(サイニィ)の使い方について説明します。
CiNii(サイニィ)とは日本国内の学術論文を検索できるデータベースです。
日本語ではサイニィが正しいのですが、実際にはサイニーと使っている方のほうが多いようです。
サイニィでは日本国内の研究者が書いた論文をいっぺんに探すことができます。
以下の画面で探したい論文の検索ワードを入れるだけなのです。
なお、検索ワードは必ずスペースをあけて入力してください。
たとえば、インバウンド政策について調べたいと思った場合、「インバウンド 政策」と入れると189件の結果が出ますが、「インバウンド政策」と検索すると44件しかでません。
つまり、「インバウンド 政策」と検索すると両方が使われているどこかに使われている論文が検索できますが、「インバウンド政策」という単語しか検索できません。
サイニーでの文献の探し方は以下の動画と文献の探し方【CiNii】で詳しく解説しています。

▶ サイニィの使い方の動画 (新しいタブで開きます)
Google・Google Scholarの使い方
論文だけでなく、政府などが出している統計資料など、まだ、論文になっていない資料などを調べたいときがありますが、そのようなとき、このやり方はとても便利です。
Google上で検索ワードの後に.pdf をつけるだけです。たとえば、インバウンドに関する資料を探したいのなら、「インバウンド.pdf」と入力してください。そうしますとpdfがついた資料ばかりが抽出されます。
PDFの印があるところをクリックするとPDFがダウンロードできます。
また、Google Scholarとは学術論文などを探すGoogleのサイトです。
Google Scholar上で自分が探したい検索ワードを入力してください。サイニィとはまた異なる学術論文が入手できます。
もっと詳しい解説はこちらの動画で学習してください。
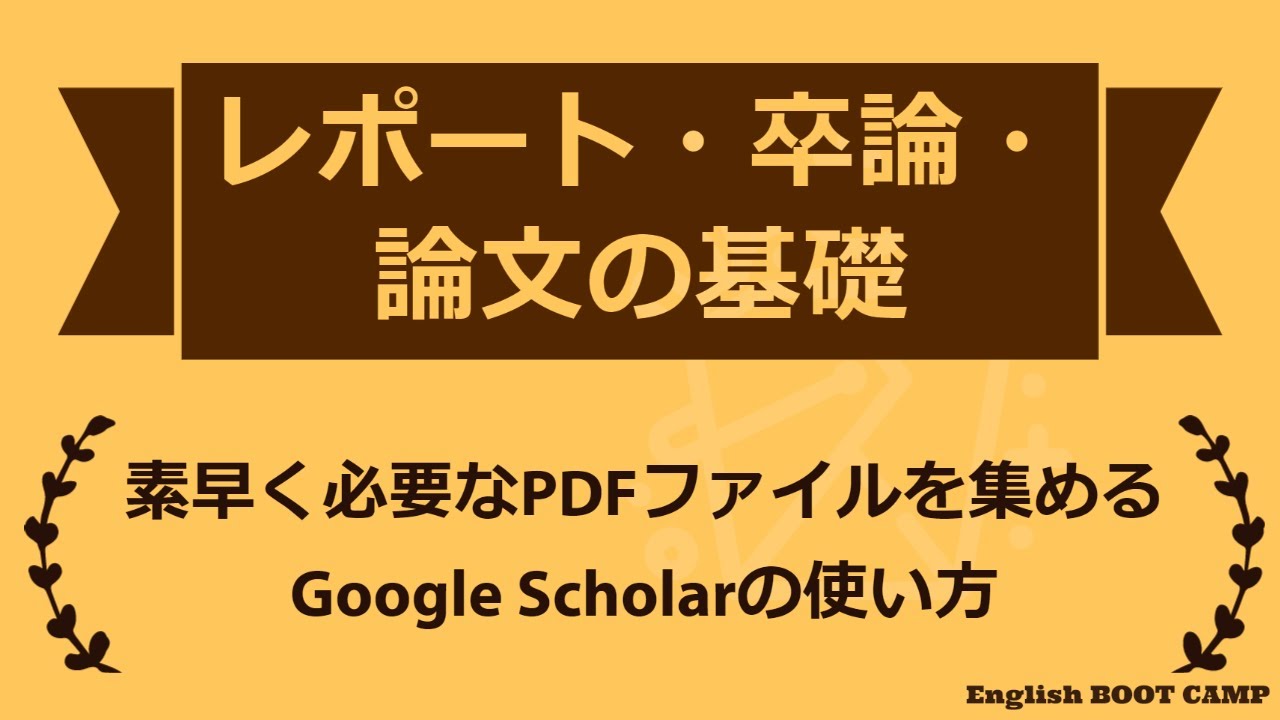
▶ Google Scholarの使い方の動画を見る (新しいタブで開きます)
国立国会図書館を活用
その他、国立国会図書館も利用することができます。
国立国会図書館には、日本で出版された書籍・新聞・雑誌などが保管されており、手続きをすれば閲覧することができます。
ちなみに、国立国会図書館は、東京館(東京都)・関西館(京都府)にありますが、わざわざ行く必要はありません。
私自身も国立国会図書館は実際に行ったことはありません。
オンライン上で申し込む複写サービスがありますので、日本中どこでも利用できます。
論文はその1つで、複写サービスを利用するとページを指定して複写を入手可能です。
また、本については郵送での貸し出しは行っていないのですが、ほかの図書館への貸し出しは行っています。
自分が住む近くの図書館か大学の図書館が図書館貸出制度に加盟している場合には、それらの図書館に図書を貸し出してくれるので、そこに出向くことで資料を閲覧することができます。
また、国立国会図書館のホームページには、資料の調べ方がものすごく細かく解説してあります。
また、国立国会図書館のサイトではありませんが、統計を調べるにはこちらが便利です。
各県市町村などのホームぺージ
個人が書いたブログなどを先行研究として引用することはできませんが、公的な機関が出しているホームぺージは先行研究として引用することができます。
特に、観光・地方創生・地域活性化・SDGsなどについて研究している方で、自分の住んでいる地域や関心のある地域について論じる場合は、必ず、各県市町村のホームぺージや観光協会などをチェックして情報を収集しましょう。
たとえば、箱根町などはこのように卒論を書く学生のために、まとめてくれています。
観光・地方創生・地域活性化・SDGsに関しては以下の2つを参考にしてください。
自分の就職したい地域の卒論を書いて卒論の面接で利用するということもできます。
卒論と就活に関しては、以下の2つを参考にしてください。
Amazonを活用して関連書籍を探す
研究テーマを深めるには、まず一冊、自分の興味に合った専門書を見つけることが大切です。Amazonは書籍数が豊富で、大学図書館では見つからない資料や、品切れの専門書も入手しやすい点が魅力です。
特に卒論のテーマに悩んでいる学生には、「Amazonで気になる本を1冊選び、その本の参考文献を手がかりに先行研究を調べていく」という方法をすすめています。本という確かな土台から始めることで、資料収集の方向性が明確になり、論文の構成も安定します。
また、学生の方はPrime Studentを活用すると、月250円・年間2,450円(税込)で以下のような特典を利用できます。
- Prime Student:追加料金なしでお急ぎ便が使い放題。次の日、または時間帯によっては当日到着することもあり、急ぎの資料購入に非常に便利です。
- Prime Video:追加料金なしで対象の映画やTV番組が視聴可能。HuluやNetflixを契約しなくても多くの映画・ドラマを無料で楽しめます。
- Prime Music:200万曲以上が聴き放題。勉強中のBGMにも最適です。
- Amazon Photos:無制限のフォトストレージが無料で利用可能。研究ノートや資料画像のバックアップにも便利です。
そのほかにも特典があります。詳しくはアマゾンのPrime Student公式ページをご覧ください。
なお、一度申し込むと4年半更新しなくても利用でき、卒業後に申し込む場合の約半額で利用できます。在学中に登録しておくのがおすすめです。
まとめ
この記事では、レポート・卒論・論文における資料・文献の効率的な探し方と集め方を紹介しました。
信頼できる資料を集めることで、論文の質は格段に向上します。ぜひ今回紹介した方法を活用して、効率よく執筆を進めてください。
引用方法や参考文献の書き方については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、各パートの書き方に不安がある方はこちらの記事も参考になります。
卒論が進み始めたら、次は将来の準備もスタートしましょう。
- 【英語×スキル習得】プログラミングを英語で学ぶならKredo オンラインキャンプ
- 【資産形成の第一歩】大学生のための新NISA&積立NISA完全ガイド
- 【学業効率UP】中古パソコンの選び方とおすすめ店舗比較






